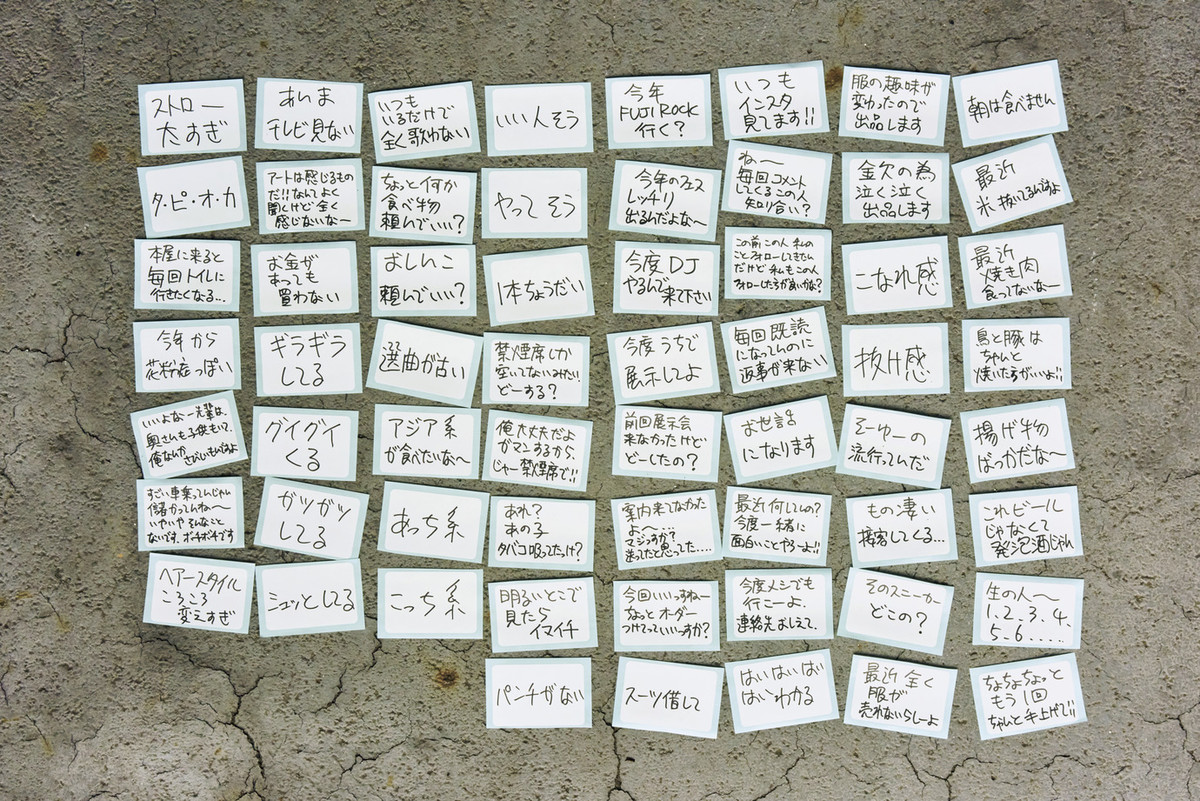
言葉のイメージや意味の変質
2020年4月14日 (火)
今朝はあまり良く眠れず、早朝に目が覚めてしまった。
カーテンを開けると雨もあがって天気もよく、人もほとんど歩いていない。それならば、お昼ごろに予定していた買い出しを今済ませてしまおうとそのままスーパーマーケットへ買い出しへ出た。
部屋からの眺めの通り、家の前の通りも、スーパーマーケットもガラガラに空いていた。
買い物を済ませて、ほとんど人がいない街をゆったり散歩しながら、家へ向かう。時々すれ違うひととお互いに距離を保ちながら、閑散とした街を歩いていると、空間と時間を共有しているという感覚を覚えた。
不思議な感じだ。
自分にとって近年の共有という言葉には、「1つの事柄を大勢で分け合う」という密なイメージがあった。よりよく共有し分け合うためには、物理的にも情報的にも密に集まることが必要なイメージがあったのだ。
時間というリソースは有限で、1日という単位に絞ればたったの24時間しかない。その枠の中で家事を済ませ、仕事をし、睡眠をとり、家族や仲間とコミュニケーションして、最低限の必要な用事を済ませるために外出する。
外出するための時間はさらに絞られるから、出かける時間は他の人と同じ時間になりやすい。
早朝に買い出しへ出たことは、この限られた時間を他の人とずらし、オンタイムであれば自分が専有していたであろう空間を他人に譲ったという感覚を覚えたようだった。譲るという言葉もおこがましいが…。
何かを譲るためには事前に価値を共有していなければいけない。どうもこの非常時で時間と空間を他人と共有できているという感覚が無意識にあるらしい。非常時の防衛本能だろうか。一体感という言葉にそら恐ろしいものを感じるが、悪いことだとも思えない。
時間というリソースを共有した結果、譲り合いが生まれ、空間というリソースが疎になるという現象が発生しうるという可能性に驚いている。
集団や集合におけるムーブメント(所謂、流行)ではなく、個の判断で自発的に、自律的に行動することでこの危機を乗り越えられたらよいと思う。
言葉の意味やイメージは時代によって変化していく。いま、僕らはその変化の現場に居合わせている。
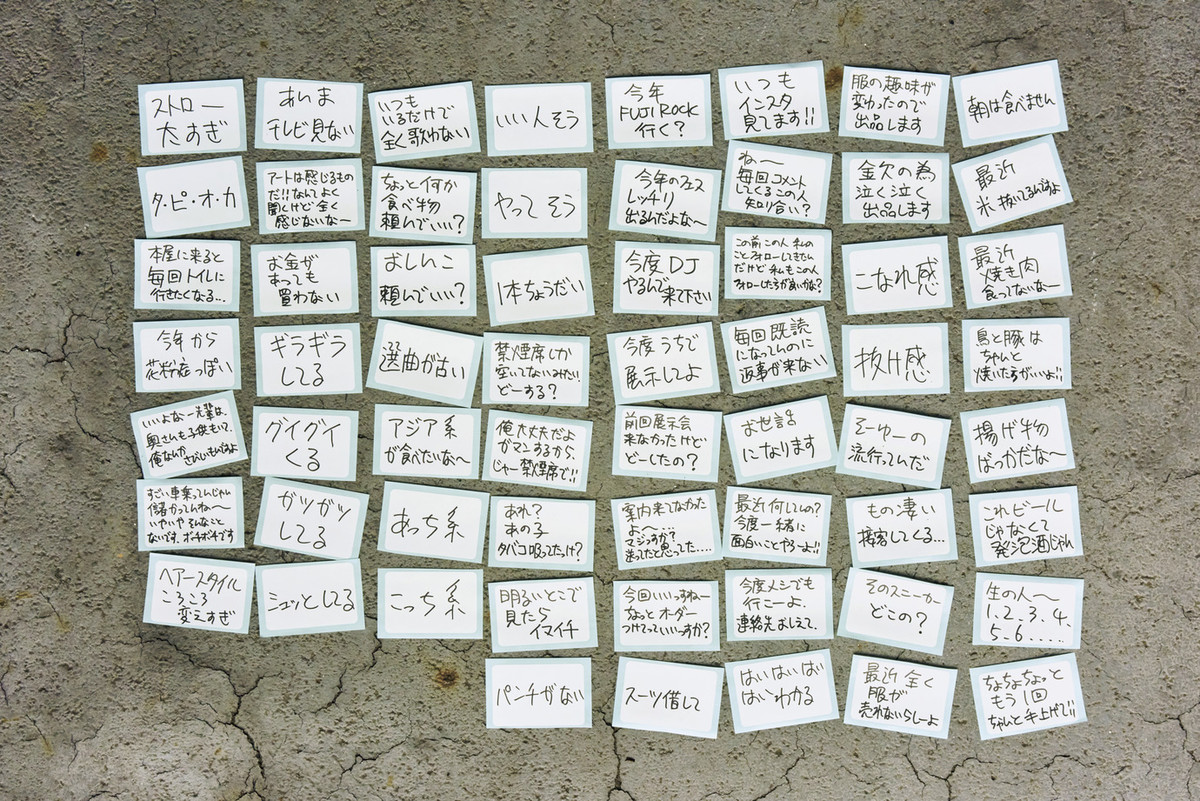
この記事へのコメントは終了しました。
コメント